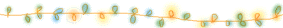
ある日のこと、ダークなブラックエースくんは、ぶすったれながら小言と嫌味を言いました。
「はぁ。全く腹が立つ! なんでこの俺様が、そんな女言葉を使わねばならないんだ!」
すると、外面仮面のホワイトアイちゃんは、キュラレストスマイルに乗せて、とてもふてぶてしい言葉を返します。
「え、素敵でしょ? 大体エースくんはさ、口ばっかりの小心者じゃない?」
凄まじい一触即発ムードがその場を包み、バチバチと火花が飛び散ります。
そんな状況に耐えられなくなったピューボロスくんは、二人の間に割り込んで提案を出しました。
「お、お主たちのどちらが優れているか、力比べをしたらどうかね?」
「ピューくん、それは名案ね! エースくん、正々堂々戦おうね!」
「えぇ? めんどくさっ! でもま、仕方ないからやってやるよ!」
こうして、ピューボロスくんの提案により、二人は意地をかけた力比べをすることになりました。
「では、あそこで爆睡している鈴の、パジャマを脱がせたほうが勝ちというのはどうだ?」
「なんだそれ? めちゃくちゃ簡単じゃねーか。じゃ、俺が先行でとっとと勝負をつけちまおう」
「ご自由にどうぞ? 頑張ってね、口だけエースくん♪」
エースくんは、力を込めて鈴ちゃんに何かを囁きます。
脅しをかけて、鈴ちゃんのパジャマを脱がそうというのです。
ところが、鈴ちゃんはパジャマを脱ぎません。
「えー。嫌だよ寒いもん……」
エースくんは、さらに力を込めて鈴ちゃんに怒鳴ります。
「いいから、サッサと脱げっ!」
ところがパジャマを脱がせるどころか、鈴ちゃんは寒がって毛布の中に潜り込んでしまったのです。
「絶対に嫌だもん! 寒い寒い〜!」
「こ、この寒がり雪だるま女っ! もういい!」
エースくんは心底呆れ果て、捨て台詞だけを残し、諦めてしまいました。
「やっぱり口だけエースくんは失敗ねぇ〜。じゃ、今度は僕の番ね?」
アイちゃんはそう言うと、サンサンとキュラレストスマイルを輝かせ、鈴ちゃんに近づきます。
「鈴ちゃん、身体があったまるからコレを飲もうねぇ♪」
そう言いながら毛布をめくったアイちゃんは、何やら怪しげな液体を、鈴ちゃんの口に流し込みました。
するとどうでしょう!
鈴ちゃんの身体がストーブのように赤々と燃え始め、冷え切った寝室をみるみると暖めていくではありませんか!
「ア、アイちゃん? なんかすっごく身体が熱いんだけど、ま、また何か変なものを飲ませ……」
鈴ちゃんはそう言いながらも、意思に反してパジャマを脱ぎ、とうとう丸裸になってしまったのでした。
「い、いやぁ〜! な、なんでぇ〜! 身体が勝手に〜っ!」
そんな光景を見続けていたエースくんとピューボロスくんは、腑に落ちない疑問を口にします。
「正々堂々ってお前は言ったよな? これはどう見ても、不正堂々だろうが!」
「お、お主には、良心の呵責というものがないのか……」
「いやだな二人とも。ここは、『俺の負けだ……』って言うところでしょ?」
「絶っっ対に言わねぇよっ!」
「勝敗を見極められん……」
こうして、誰一人として反省するものなどなく、それからも鈴ちゃんをめぐって、醜い争いを続けます。
そう、それは、寒い寒い真冬の夜のことでした――
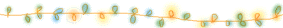

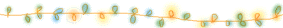
「寒い〜っ! 寒い寒い寒い寒い寒い……うわっ、さっぶっ!」
そろそろ寝ようと思い立ち、暖房のスイッチを消した途端に襲いくる、キーンと冷えたかき氷空気。
日本の冬はこんなに寒かったかと過去を振り返り、ブルブル震えながら文句を言った。
自慢じゃないが、私は寒さに滅法弱い。
万年常春ココア国のお姫様だからと言ってしまえばそれまでだけれど、私はそこで生まれ育っちゃいない。
というか、今でもそんな自分の境遇に半信半疑のままだ。
けれど、そんな私にエースが必ず言う。
「頭の中だけは、充分にココアのお姫様だけど?」
私の頭の中が、万年お花畑だといわんばかりの鋭い嫌味。
それじゃココア国の民は、皆が皆、年中無休の春爛漫みたいで気に入らない。
だから、春とは無縁そうな人物の名前を挙げて反論を試みる。
「アルの頭は、春じゃないもん!」
けれどエースは、どこから声を出しているんだというほどの甲高い笑い声を吐き出してから、霜降り肉より極上の思想を披露した。
「クーッ! あいつの頭は、常秋だろうに? 哀愁と黄昏で乗り切る365日?」
「そ、そんなことっ!」
ありえそうで、なにやら恐ろしい……
キルティングのババシャツと股下を装着し、その上からフリース素材のパジャマを着込む。
それでも寒さは全く治まってくれないから、遠赤外線靴下にレッグウォーマーを穿き、マフラーと手袋は必要だろうかと考えて、はたと気がついた。
「あれ? 私、寝るつもりじゃなかったっけ?」
肩をすくめて照れ笑いを浮かべるけれど、ギャラリーなど誰も居ない。
仕方がないから、羽毛97%配合の上掛け布団をビシッと指差し言い放つ。
「消えた3パーセントの謎は、必ず私が解いてみせる。羽毛布団の名にかけてっ!」
「……さぶっ!」
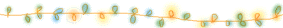
アイちゃんの居ないベッドは、広々としすぎてなんだか寒い。
特に横向きへ寝返りを打ったときなど、背中にできた空間がたまらなく寒い。
だから、何人でも眠れそうな広いベッドで、ダンゴムシのように丸まって眠る。……けれど寒い。
アイちゃんは、近頃富に帰宅が遅い。
どうせまた、エースとしてバールへ赴いているのだろうけれど、人間界へ帰ってくると、極端に性格や口調が変わるから驚きだ。
きっとこれも、紫ババアの怨念に違いない……
ところが今日に限って、心地良い眠りについている私を、揺さぶり起こすのはエースの声。
「ベル起きろ。そしてパジャマを脱げ」
こんなに寒いのに、しかもようやく身体が温まってきたというのに、パジャマを脱ぐことなんて考えられない。
だから、毛布を海苔巻きみたいに身体へ巻き付けて、回転しながらボソボソとエースに呟いた。
「えー。嫌だよ寒いもん……」
エースが次に起こす行動など、あの男に比べたらどうってことはない。
まず怒鳴り、それでも私が言うことを利かなければ、キーキーと捨て台詞を残して立ち去るはず。
言葉で訴えば、誰もが思い通りに動いてくれる身分なだけに、それ以上の行動を取ったりしないのがミソだ。
そして、そんなミソに気がついた私は、麹味噌より素晴らしい。
「いいから、サッサと脱げっ!」
「絶対に嫌だもん! 寒い寒い〜!」
「こ、この寒がり雪だるま女っ! もういい! お前なんかバケツでも被ってろっ!」
ほ〜ら、言った通りだ。
寝ぼけながらも作戦を遂行できた私は、天性の才能があるに違いない。
けれど私は、肝心なことを忘れていた。
ここは人間界だ。つまり、エースを怒らせると、代わりに現れるのは……
「鈴ちゃん、身体があったまるからコレを飲もうねぇ♪」
いきなり毛布を捲られて、ゾクっとする空気が私を包み込む。
目を開けなくても解る。眩いばかりの笑顔を引き連れた、キュラキュラ大魔王の降臨だ……
言葉だけでは、世の中を渡って行けないと悟った男。
腕力や飛び道具でも望む天下は取れないと判断し、新たな武器を自ら生み出した最強な男。
この男の笑顔は、麻酔銃より強力だ。
そして、神々しいほどのキュラレストスマイルが放たれたとき、それは私の絶体絶命を指す……
薄っすらと目を開けたものの、その余りの眩しさにクラクラし、手を翳して光を遮った。
けれどそんな私の手を意図も簡単に払い除け、アイちゃんの冷たい唇が、私の唇に重ねられる。
「ふぅっ…んぐっ!」
の、飲んじゃった……
余りの早業に思考回路は追いつかず、アイちゃんの口に含まれていた妙な液体を、溢すことなく飲んじゃった。
メープルシロップみたいな、ちょっと香ばしい感じの甘くてトロっとした蜜の味がジワジワっと広がって、その途端、穴という穴から、蒸気が発射されちゃうほど身体が熱くなる。
「ア、アイちゃん? なんかすっごく身体が熱いんだけど、ま、また何か変なものを飲ませ……」
ところが、そんな解りきった台詞を言い終わる前に、アイちゃんがおかしなことを言い出した。
「右手を上げて。右手を下げて」
「な、なにを、ア、アイちゃん、あれ? おや?」
意思に反して、アイちゃんの号令通り、腕が勝手に動き出す。
「右手上げて、右手下げないで、左手上げて、右手下げて。って、鈴ちゃん違うでしょ!」
「い、いやぁ〜! な、なんでぇ〜! 身体が勝手に〜っ!」
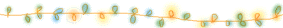
「オッケー。じゃ鈴ちゃん、パジャマをパパっと脱いじゃってね?」
どうやら私は、旗揚げ試験に合格したらしい……
なんて、悠長なことを言っている場合じゃない。
アイちゃんの号令が絶対であるように、私の指はパジャマのボタンを素早く外す。
「あれれ? 鈴ちゃんそれは、ちょっと着込み過ぎじゃない?」
パジャマの下から現れた、あったか素材のシャツを見て、ゲンナリしながらアイちゃんが文句を言うから
「さ、寒いから、私は脱いだりしたくないのに〜!」
そんな戯けた台詞を叫んでみるけれど、結局はシャツまで脱ぎ始める私の身体。
そこでまたキュラレストスマイルに乗せて、アイちゃんが訳の分からない言葉を吐いた。
「うるさいよっ! 僕の勝ちなんだから、鈴ちゃんは僕のもの!」
「ア、アイちゃん? だ、誰に……おぉ?」
背中で手を組めと命令され、どんなに解こうともがいても、まるで手錠をされちゃったようにビクともしない私の手。
何も纏っていない胸を突き出している自分が、なんだかひどく滑稽だ。
それでもアイちゃんは、水を得た魚のようにキュラキュラしながら平然と言う。
「鈴ちゃんを、押さえつけなくて済むから楽チンねぇ」
そして、ゆっくりゆっくり私の胸に顔を近づけて、既に固く尖った先端を、下から上にレロンと舐めた。
「い、いや…ア、アイちゃん…や、やめ……ふぁんっ!」
柔らかくて温かいアイちゃんの舌が、円を描くように私の胸を弄ぶ。
当然、もう片方の先端は、アイちゃんの指でこねくり回されて痛いほど疼く。
「うくっ…んっ、あぁ…んっ……」
身を捩って喘ぎたいのに、それすら許してもらえぬこの状況。
それなのに、こんな状況を楽しみ止まないアイちゃんは、更なる試練を私に課せた。
「鈴ちゃん、足を開いて、腿を手で押さえてくれる?」
「い、いやだ…絶対にイヤ……うぅ……」
声が拒んだところで、身体は素直に足を開く。
ゴロンと仰向けで横になり、膝の裏へ手を掛けて、開いちゃった自分の足を自分の両手が押さえつけた。
ネトっとした水音を立てて、口が開いた感覚に恥ずかしさがこみ上げる。
アイちゃんは動くことなく私を見ているだけなのに、見られていると思うだけで、トプンと溢れてくる甘い蜜。
そんなヌルヌルした蜜が冷たい空気に晒されて、ヒクヒクと浅い呼吸をするたびに、肌を伝って流れ落ちていく。
アイちゃんの指が、ようやく私の蜜を絡め取り始めた。
もうそれだけで、興奮の波が中心から波紋を描く。
けれどアイちゃんは、本当に蜜を絡めただけだ。
私には直接触れず、蜜の上にそっとそっと指を滑らせる。
「ふぐ〜っ……はぁ…んっ…ふぐ〜っ」
欲求不満が喘ぎ声が私の口から零れ出て、剥かなくても既に姿を現しているであろう敏感な突起を、どうか触ってほしいと懇願する。
いや、正確には触って欲しいどころじゃない。
強く、早く擦って、あの痺れるような快感を味わいたいんだ。
けれどアイちゃんは、ギリギリのラインで指を止め、また触るか触らないかのタッチで来た道を戻っていく。
「くぅ〜っ!」
これ以上、こんなことを続けられたら、焦らされ死にしてしまいそうだ。
でも、こんな姿で死にたくない。
だから意を決して、完全白旗宣言を吐き出した。
「ア、アイちゃん……お願い…お、お願い……」
ところが、そんな私の言葉でアイちゃんの態度が急変する。
「俺がお願いしたとき、お前はイヤだってほざいたよね?」
こ、この口調と一人称は、紛れもなく……
「え、エ、エース? あ、や、お願いはされてない……はぁっ!」
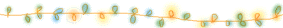
「んっあぁぁぁぁぁ〜っ」
指を通り越し、攻撃的なエースの舌が、充血しまくった私の突起を攻め立てる。
さっきまでは、焦らされ死にしそうだったのに、今は感電死しそうな勢いだ。
舌で舐めるとか、転がすなんて、可愛らしい表現では追いつかない。
きっと私はこのまま、エースに食べられちゃうんだ……
「あぁぁっ! ダメっ! ……い、いや! いやぁぁぁぁっ!」
エースの口が私の蕾を思い切り吸い上げて、そのまま顔を何度も横に振る。
さらに、一本じゃない指が差し込まれ、ピチャピチャと激しい音を立てながら、私の中を凄い速度でこねくり回す。
ビクンビクンと身体が揺れて、何度も絶頂を迎えているのに、グッタリすることも許されないまま、依然として両手は自分の足を掴む。
指の動きを止めることなく、体勢を変えたエースが、私の耳元で囁いた。
「足は開いたまま、腕を突っ張って起き上がれよ。お願い」
取ってつけたようなこのお願いは、お願いなんかじゃ全然ない。
なのにやっぱり私の身体は、エースのお願い通りに勝手動く。
足を掴んでいた両手はストンとベッドの上に落ち、そのまま力を入れて突っ張り始め、カクカクと震えながらも上半身を起き上がらせていく。
こんなことをさせてどうする気だと、ちっぽけな頭で考えた瞬間、またもや囁かれるお願いじゃないお願い。
「見て。お願い」
「んっあぁっ…やっ! くぅっ……ダメ! あっ、あっ、いやぁぁぁっ!」
根元までテラテラと濡れたエースの指が、激しく、妖しく動くその光景。
視覚にまで訴えかけられて、感度は通常よりも数倍増していく。
さらに起き上がっちゃったことで、その指が確実に一番ダメなところにフィットした。
「んんんっっ! ダメ〜っ! そ、そこ…いやぁ〜っ!」
「イヤじゃなくて、イイの間違いだろ?」
陸に上がった魚のように、ビクビクと身体が飛び跳ねる。
こうやって何度も崖から飛び降りているのに、地面に着地することなく引き戻され続けるから、感覚が完全に麻痺した私は、もはやどっちが上で、どっちが下かもわからない。
なのに、依然として指の動きを止めてくれないエースは、さらなる刺激を与えるために、私の胸を口に含んで弄ぶ。
「くぅっ……! いやぁぁぁっ!」
これ以上、こんなことを続けられたら、狂い死にしてしまいそうだ。
でも、こんな姿で死にたくない。
だからまたもや意を決して、完全降伏宣言を吐き出した。
「エ、エース……お願い…お、お願い……」
ところが、何かの呪文なのか、この言葉を発した瞬間エースの態度が急変する。
「あぁもう! 僕のジレジレ作戦が水の泡じゃない!」
こ、この口調と一人称は、紛れもなく……
「あ、ア、アイちゃん? あ、や、な、なんで…うぅっ!」
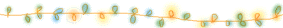
「また最初っからやり直しね? じゃ、鈴ちゃん腕を上げて?」
「やっ…おぉっ?」
ベッドに突っ張っていた腕が突然なくなって、上半身がマットの上に沈みこむ。
そして今度は、『前習え』みたいに、アイちゃんへ向けて伸びる私の腕。
そんな私の腕の間にアイちゃんがスルっと入り込み、開きっぱなしの私の膝を畳んで胸に押し付けた。
「んんっ! ……うぅ?」
チュポっと音を立てて、アイちゃんの先端が私の中に差し込まれた。
けれどいつものように、奥まで入ってこないから拍子が抜ける。
アイちゃんの目線は、確実に結合部分へ落とされていて、畳まれた私の膝に手を置きながら、中途半端な抜き差しを延々と繰り返す。
「ア、アイちゃ…アイ……ふくぅっ」
一定のリズムで響く、チュポチュポという軽い音。
このどうにもならないジレったさで、行き場をなくした興奮は溜まる一方だ。
入り口付近は、なにやらどうも、そこまで気持ちよくはない。
快感に溺れることがないから、余計にアイちゃんのクビレや形がよくわかるんだ。
そしてそれがまた興奮に繋がって、ジレったさフルスロットルで殻回る。
「あ、ダメよ鈴ちゃん、腰を動かしちゃ」
私を見下ろしながら、アイちゃんが可愛らしく囁く。
そんなことを言われても、ちょっとでも深く入れて欲しいと、腰が勝手に浮かび上がっちゃうんだから仕方がない。
けれどアイちゃんが、動かしちゃダメだと命令したから、それからは動くことのなくなった意気地なしな私の腰。
アイちゃんが、先端だけを抜き差ししながら、ピンポイントで隆起した蕾を擦り始めた。
さっきまでは、こんなに気持ちの良いものはないと思っていたのに、内側から齎される中途半端な刺激と絡み合い、外側からのそんな刺激は、ジレったさ倍増だ。
動物の赤ちゃんが鳴くように、キューキューと鼻から抜ける声が私から搾り出る。
そんな私の頬を優しくなでつけながら、アイちゃんがシレっと言い放つ。
「僕以外でイっちゃったら許さないからね? 鈴ちゃん約束できる?」
エースとアイちゃんは、同一人物でオッケーですか?
それなら確実に、約束することができます……
「エっ、アっ、どっ、オっ……や、や、んっ」
懸命に想いを伝えようと頑張るけれど、途切れ途切れの言葉だけしか吐き出せない。
だから何事もジェスチャーが大切だと、何度も何度も小刻みに肯いた。
「ぐぅあぁっ!」
ズンって地鳴りがするように、アイちゃんが深く私を貫いた。
予期せぬたった一突きで、軽く果てちゃう私の身体。
ここで重要なのは、あくまで軽く果てちゃったってことだ。
なぜなら、アイちゃんは奥まで突刺したままピクリとも動かないからだ。
「本当に約束できる? できないなら、このまま動いてあげないよ?」
だめだ。また言っちゃいそうだ……
これ以上、こんなことを続けられたら、悶え死にしてしまいそうだ。
でも、こんな姿で死にたくない。
だから解っていながらも、完全懇願宣言を吐き出した。
「ア、アイちゃん……お願い…お、お願い……」
そして当然、そんな私の言葉でアイちゃんの態度が急変する。
「相坂以外では、イかないって、約束してたよね?」
そ、そんな約束を、交わした覚えなどないんですが……
「エ、エース……ダ、ダメ…もうダメ……あっ!」
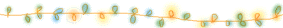
「あぁっ、んんんんあぁっ!」
畳まれた私の膝を斜めに倒し、横向きな角度でエースの打撃が始まった。
掴むものを探す私の手は空を泳ぎ、結局、枕を握り締めて発狂する。
ダメだ。気持ちが良すぎておかしくなりそうだ。
あれだけ焦らされ続けた後の、こんな激しい連打に、身体が反応しないわけがない。
それなのに、エースの意地悪声が低く低く吐き出され、ゾワゾワ感を引き連れながら私へ届く。
「イかないんだよね? 俺じゃ、イけないんだよね?」
「くぅっ…! あぁっ あぁっ あぁっ ふぅっ!」
イっちゃうのは簡単だ。それでもイっちゃった後が怖い……
だから全身を硬く強張らせて、押し寄せ続けるイっちゃいそうな波を、懸命に乗り越える。
なんだかもう、どうしていいのか解らず泣き出したくなってきた。
けれどエースには、そんな私の考えなどお見通しだ。
イヤっていうほど感じる場所を、深く抉りながら速度を上げる。
「あぁぁぁっ! ダ、ダメ……そ、そこ、ダメーっ!」
爪の先までビリビリと痺れる、圧倒的な気持ちよさ。
こんなところを突かれたら、我慢なんてできやしない。
だからエースの胸を叩いて、どうにかやめて欲しいと訴えるけれど、このエース様が止めてくれるはずなどない。
「ダメ…ダ、ダメッ、イ、イッ…あっ、ダメーっ!」
もうダメ。もう限界。激しすぎる。気持ちよすぎる……
「ご、ごめ…ごめっ、ゴメんんあっ! ダメ…ゴメ、ダメ、ゴメ……」
なんだかよく解らないけれど、謝るから許してください。
もうダメなんです。何がダメなのか解らないけれど、ダメなんです。
そしてトドメは、この一言。
「イけ」
歯を食いしばるエースが吐き出す言葉で、スイッチが入っちゃった……
「イ、イクっ……んあぁぁぁぁぁっ!」
恍惚感に浸り、真っ白な世界を漂うこと、ほんの数秒。
瞼を持ち上げた先には、キュラキュラな金色の世界が待っていた……
「鈴ちゃん、僕以外では、絶対にイかないって約束したよね?」
「ぜ、絶対とは言ってな……んんんあぁぁぁぁっ!」
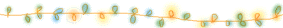
「うわぁぁぁっ!」
97%羽毛を払い除け、素晴らしい腹筋具合で飛び起きた。
身体中、汗をかきまくってビショビショで、動悸は止む気配がない。
即座にパジャマを確かめ、ババシャツを確かめ、ついでにアイちゃんの枕の凹み具合も確かめた。
けれど汗をかいている以外は、眠る前と何一つ変わっていない。
「な、なんて恐ろしい夢を見たんだ……」
恐ろしすぎる悪夢から目覚め、現実に戻った途端に襲いくる究極の寒さ。
これでもかってなほど、汗をかいちゃっているから仕方がない。
華麗かつ優雅に手を顎に当てて、汗の原因追及に勤しむけれど、当たり前だがギャラリーなど居ない。
仕方がないから、レッグウォーマーと靴下を脱ぎ捨て、お決まりの文句を叫ぶ。
「遠赤外靴下が犯人だっ! 真実はひと〜つっ!」
「……さぶっ!」
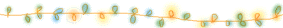
こうして鈴ちゃんは、いそいそとまた布団の中へ潜り込みます。
そして、今度こそは、素敵な夢が見られるようにと、呪文を唱えて眠りにつきました。
けれど鈴ちゃんは、大事なことを見逃していたのです。
そう、ベッドサイドに置かれたゴミ箱の中は、丸まったティッシュでいっぱいだったことを……
寒い寒い真冬の夜。
凍えるあなたを、温めてくれるのは誰ですか……?
Fin.....
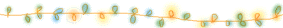
Index|Main|Novel|Cappuccino