肌に纏わりつく長い髪と、くぐもる世界の音に、濁った視界。
息苦しさを感じながら、どこまでも続く深い底へ止まることなく墜ちていく。
淡かった碧海は、いつしか濃く蒼く深まり、孤独と不安に苛まれた私は、その深き蒼へと闇雲に両手を伸ばした。
冷たく硬い何かが指先に当たり、もう一度それを確かめようと目を凝らしながら弄れば、突然右方から眩い光が差し込み、目の前に磁器のような肌合いのつややかな円柱が現れた。
夢中でその柱にしがみつき、自分の口から吐き出される無数の泡を目で追う私に、眩い光が語りかける。
『夢から覚める? それとも此処に来る? 選ぶのは晴香だよ……』
これは夢。けれど夢から覚めた現実もこれと大差ない。
悲しいほどの孤独は、一時でも私から離れることがないのだから……
だから不安に震えながらも、光に向かって呟いた。
『覚めなくていい……』
泡という名の言葉を吐き出しながら柱を滑り降り、光の下へと続く壁に手を翳す。
施された彫刻で凹んだ箇所に指を掛け、ゆっくりと着実に光の中へ飲み込まれていった。
光の中央に、藍色のヴェールを被った老婆が揺らめいている。
老婆は私の姿を見て取ると、驚く素振りも見せず、口を閉じたまま重く深い声で語った。
『お前の望みは何かね?』
私の言葉は泡となり、口元を旅立った瞬間、弾け消えた。
それでも老婆は了解の意を込めた頷きを見せ、私へ向かって小瓶を放る。
小さな泡を伴って、重力に負けることなくゆっくりと、小瓶が私の手中に納まった。
両手のひらで包み込んだ小瓶を訝しげに見下ろせば、肌を伝って響く老婆の声。
『取引だよ。それを渡す代わりに、私はお前の声を貰う。お前の願いが叶えば、声を返してやろう。けれど叶わなければ……』
髪が波打つ。視界が狭まる。世界が揺れる。
頭上から段々と淡い碧さが戻り、夜の終わりを告げ始めた。
夜が終わる。それは、夢が終わりを迎えるとき。
『それを飲むか飲まないか、選ぶのはお前。私はそれに従うさ』
老婆の最終通達が急かすことなく齎され、そして私は小さな泡を吐き出しながら、手にした小瓶の蓋を開けた――
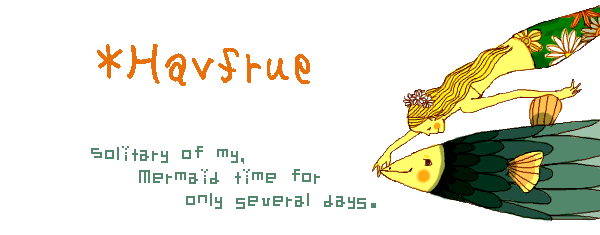
数多くある童話の中でも、私は人魚姫の物語が一番苦手だった。
悲恋云々よりも、多くの誤解と歪んだ事実を、誰一人として正す者が居ないところに腹が立つ。
大体、優しい姉たちと美しい城で暮らし、何一つ不自由などないはずなのに、自分の境遇を悲観し、恋愛に比重を置く生き方が納得できない。
真実を見抜く力量すらない見てくれだけな男のために、自分の命を賭けるだなんて考えただけでも悪寒が走るし、 泡になる瞬間、奇蹟が起こったという割に、三百年もの善行を積むことが課せられるなんて滑稽過ぎだ。
ところが、変な夢から目覚めると、まるで一泳ぎでもしてきたかのように髪もベッドもズブ濡れで、身体は麻痺して動かない。
そして、最も驚いたのは……
『私としたことが、愚かな骨の頂だな。って、あれ?』
そう。声が出なくなってしまったことだった――
数週間前から、喉の痛みを感じていた。
けれど、どうせいつもの風邪だろうと考え、放置したのが災いらしい。
それでも嘘のように痛みは消え、唾も余裕で飲み込める今の状態は、悪化したというよりも回復期に差し掛かった按配だろう。
それに別段、声など出せなくても、困ることは何もない。
床に足を下ろし、ゆっくりと立ち上がるけれど、足に全く力が入らず、そのまま成す統べなく転がった。
痛みを訴えたところで声は出ず、フローリングに思い切り打ち付けた場所を顰め面で摩る。
それでも気を取り直し、蛇のように這い蹲りながら、磯臭さが漂う身体を洗い流そうと、必死で風呂場へ向かった。
私の部屋は、いつから宮殿並みの広さになったのだろう。身体全てに力が入らないから、風呂場までのほんの数十歩が、山の二つ向こうに思えるほど遥か遠い。
『タクシーを呼ぶか? いや、声が出ないから呼べないな……』
思考能力はいつもの数十分の一まで下がり、動かないと知りながら、そんな自分の身体を拳で叩き続けた。
ようやく辿り着いた風呂場でも、然程小さくもないパジャマのボタンが外せない。
それでも、苛立って引き千切りたくなる衝動と戦いながら、懸命に上二つだけを外し終えた。
全てのボタンを外すことなど疾うに諦めて、声が出ないことをいいことに、喚き散らしながらそれを脱ぎ、変な角度で足を折り曲げたままシャワーの下に潜り込んだ。
ぼやけ続ける視界の中、手探りでシャンプーを探し当て、ポンプ上の凹凸を確認してほくそ笑む。
『きっといつか、こんな素晴らしいマークを発案した人に礼状を送ろう』
親指で何度も凹凸をなぞりながら、感謝の意を込めて口だけ動かした。
とにかく、何をするにも根気と必死さが要求される。
思い通りに動いてくれない身体は当然。それに加えて意識も朦朧としているだけに、要所要所の記憶が飛びぬけて、自分が今何をしていたのか、そんなことすら思い出せない。
必死で海綿を握り締めて顔を擦り、その痛さではたと我に返る。
けれど我に返れるのは一瞬で、またどこかの世界へトリップする意識。
そんな曖昧な頭の中で、大好きな歌が延々と流れていた。
鼻歌すら出せない状況で、首だけがリズムに乗って小刻みに動く。
それでもそれが、一番盛り上がる箇所でピタっと鳴り止んでしまうから、シャワーの飛沫を手で撥ね退けながら小言を呼吸し、 曲の続きを心の中で口ずさむ。
ところが、やはり一番盛り上がる箇所で、またもや唐突にその歌が始まった。
そこでようやく、その歌が携帯の着信音だということに気がついた。
手近なバスタオルをのろのろと胸に巻きつけ、タオルハンガーに肘を掛けながら必死で脱衣所に足を踏み入れるけれど、相変わらず足の麻痺は治まらない。
スライディングする寸前に、洗濯機上に置かれた携帯を握り締め、そのままうつ伏せで狭い脱衣所を滑り、終にドアへ体当たりした。
痛みを喚きながら親指の感覚だけで携帯を操作し、いつもの調子で『もしもし?』と言ってみるものの、当たり前だが声は出ない。
それでも夢の中と同じように、くぐもった声が携帯の向こうから流れ出す。
「菊池主任? どうかしましたか? あれ、先輩?」
ところがそこで、ドアにぶつかった振動からか、棚から大量のコスメが頭上目掛けて雪崩落ち、無数の痛みを受けると同時に意識を失った――
処置室の細長い簡易ベッドで、点滴を受ける私を見下ろしながら、数期下の後輩である山下が貼り付けた笑みを浮かべて話しかけてくる。
海外事業部の若手ホープなこの男が、なぜここに居るのかなど解らない。
それでも依然として声が出ないから、何を問うわけでもなく、山下の話に首を捻りながら耳を傾けた。
「今日の経理部は酷い有様でしたよ。先輩が居ないと、全く機能しないんですね」
昔から数学が好きだった。
数字や計算は、国語のように作者の感情を読み取るなどといった抽象的な課題がなく、現実味に溢れ、答えはいつも一つだ。
けれど、そんな理由で経理部に配属される者は少ない。ほとんどの社員が、寿退社を夢見る乙女たちで埋め尽くされている。
私にだって、そんな淡く儚い夢を抱いた時期があった。
それでもそんなものは、誰にでも有り勝ちな一過性の病だと決め付けて、気付けば主任という肩書きが付いていた私。
左指にゴムサックを嵌め、右指は高速で数字キーを叩き続ける毎日。
そんな反吐がでそうな単調作業でも、数字は嘘をついたりしない。駆け引きも、裏切りもしない。
自分の口調がきついと、陰口を叩かれていることなど知っている。
無愛想だと、あれじゃ男など寄り付かないと、きっと一生独身だと、笑われているのも知っている。
そして現実は、彼女たちの囁く通りだ。
それでもそれを、悔しいなどと思う自分すらもう居ない。
ここまで来ると、悟りの境地だ。
好きなことをやって、好きなものを買って、好きなものを食べて、誰に束縛されることなく、傷つくことなく生きていける。
痛みや辛さは、一人で乗り切れる。こんなときこそ誰かに寄り添って生きたいと思うのだろうが、人間はそこまで弱くない。
忙しさだって、陣序立て、一つずつ熟していけば、軈て終わる。
誰かの手など借りなくとも、なんとかできるものだ。
それでも、そうやって誰に頼ることなく、自力で手に入れた勝利の品々を見て、こんな私でもふと思うことがある。
幸せや喜びを、分かち合える者が欲しい……
喜びを手に入れると同時に、孤独も手に入れる。
幸せを感じると同時に、孤独を感じるんだ。
「って、菊池先輩、聞いてますか?」
思考回路に割って入るその声で、ここが病院だということを思い出す。
けれどその声の持ち主が、なぜここに居るのかと疑問に思ったことは忘れていた。
「ということで、点滴が終わったら家に帰れるそうですから。でも、十日間は絶対安静だそうですよ」
そんな山下の台詞で、決算が近い今、自分が十日も仕事を休んだらどうなるのかと考え、その可笑しさに変な笑いが込み上げる。
元々、他力本願のバラバラ勝手な部署だ。
自分の仕事に責任を持つことなく、誰もが誰かに責任を押し付け合いながら、誰もが誰かに定時退社を訴えるだろう。
けれどその反面、後悔という文字も頭の中を駆け抜けた。
誰と笑い合うわけでもなく、打ち解ける努力もせず、ただ黙々と一人で仕事をこなしていた。
注意の言葉だけは淡々と吐き出し、仕事を教えることなどしなかった自分。
纏まりがないのは、自分の所為だ。
大事な時期に、長期の休みが必要とされて初めて、この事実に気がついた。
全く機能しない経理部。山下の言葉が、決して褒め言葉ではないことにも、この状況が相当な迷惑を掛けていることにも、今更ながら気がついた――
『もう大丈夫だ。悪かったな。後は自分一人でできる』
目頭に指を当て、いつもの調子で山下へ言い放ったものの声が出ない。
それどころか、持ち上げるはずの眼鏡すら指先に触れることがない。
そんな私を見て、腹に手を添えた山下が、小刻みに震えながら言った。
「もしかして、先輩の眼鏡は伊達だったとか? 眼鏡なんて掛けてないのに。くっくっ」
そして山下は徐に立ち上がると、毛布で包まれた私を軽々と抱き上げながら尚も笑い続ける。
「言っておきますが、一人で帰るのは無理ですよ。なんたって菊池先輩は、歩けないんですから」
意味ありげな山下の口調から、家での最後の記憶が溢れ出す。
確か自分は、バスタオル一枚で、脱衣所に居て……
『っ!』
みっともない自分の光景が第三者視点で脳裏に広がり、その醜態さ加減に声が詰まる。
けれど私の意思とは裏腹に、事は着々と進められていく。
手際よく会計を済ませた山下に、見たこともない黒光りする車に担ぎこまれ、毛布の上からシートベルトが嵌められた。
そして運転席へと乗り込んだ山下が、右手でキーを捻りながら囁く。
「大丈夫ですよ。全て俺に任せて、安心して眠っててください」
何も言い返すことができず、というよりは、言い返す言葉が浮かばず、蓑虫のような出で立ちで芋虫のようにシートの上で丸まった。
徐々に温かさを増す車内と、低音で響くエンジンの音と、アスファルトの凹凸を拾う小さな振動に、強烈な眠気を掻き立てられる。
そして程なく、私の意識は現実の世界から旅立った。
眩い光が私に囁く。
『選ぶのは晴香だよ……』
ヴェールを被った老婆が、掠れた声で私に告げる。
『お前の望みは何かね? 選ぶのはお前……』
外敵から身を守るはずの蓑虫殻が、音もなく、容赦なく、私の身体から剥がれていく。
力が入らないままの身体は、いつもと違う硬さのマットに沈み込む。
そんな違和感を肌で感じながらも、夢の続きに勤しんだ。
『私は何を望んだ? 私はどちらを選んだ?』
朦朧としながら必死で老婆へ問いかけるけれど、老婆の口元は弧を描くだけで、その問いに答えてはくれない。
不意に、首の下へ硬く太い幹が差し込まれた。
そしてその直後、柔らかく湿った感触が額へ宛がわれ、その温かさが身体の隅々まで広がっていく。
途端に支配力を増した感情が人肌恋しさに暴れだし、磁器のような肌合いの、温かくつややかな柱にしがみつき、柱に包み抱かれながら、夢の世界からも旅立った。
けれど、真っ白な世界から現実の世界へ戻ると、見たことのない光景が目の前に広がっていた。
『こ、ここはどこだ……』
Index|Main|Novel|Havfrue